
ご法事 移動なし (49日忌・1周忌・3回忌・納骨・改葬・位牌・仏壇供養など)

日時や場所など、依頼したい内容を記入します。
あなたの依頼に合ったプロから見積もりが届きます。
ご予算、ご希望を満たすプロを選び、採用してください。


仏事は分からない事ばかり、という方がほとんどです。 初めてと言う方もいらっしゃると思いますが、ご安心ください。 葬儀、四十九日、納骨、新盆等、色々な法要がありますが、ご依頼主の希望に沿った対応をさせて頂きます。 必要な仏具はお持ちしますので、ご安心ください。
まだ詳しい事が決まっていない。心の準備をしておきたい。 という方もいらっしゃいます。 どうぞお気軽にご相談。
お客様の年齢は様々です。ご依頼の内容も様々。 法要は亡くなった方の為だけにあるのではなく、ご親族のご納得や安心の為でもあります。 仏事に慣れた方などいらっしゃいません。何よりも故人を想う気持ちが大切です。 詳しくご事情を承り、丁寧に進めて行きたいと思っています。
急な依頼にも関わらず対応してくれた。 悲しみや不安を和らげてくれた。 スムーズな対応をしてくれた。 など、感謝の声をたくさん頂き、この仕事をやって本当に良かったと日々思っております。
まずはスムーズで丁寧なやり取りを心がけています。 ご依頼主のお気持ちに沿う事が何よりと考えます。 お布施という分かりにくい料金設定も、明確な金額を提示させて頂きます。
その他特長などの紹介
仏事は分からない事ばかり、という方がほとんどです。 初めてと言う方もいらっしゃると思いますが、ご安心ください。 葬儀、四十九日、納骨、新盆等、色々な法要がありますが、ご依頼主の希望に沿った対応をさせて頂きます。 必要な仏具はお持ちしますので、ご安心ください。
まだ詳しい事が決まっていない。心の準備をしておきたい。 という方もいらっしゃいます。 どうぞお気軽にご相談。
お客様の年齢は様々です。ご依頼の内容も様々。 法要は亡くなった方の為だけにあるのではなく、ご親族のご納得や安心の為でもあります。 仏事に慣れた方などいらっしゃいません。何よりも故人を想う気持ちが大切です。 詳しくご事情を承り、丁寧に進めて行きたいと思っています。
急な依頼にも関わらず対応してくれた。 悲しみや不安を和らげてくれた。 スムーズな対応をしてくれた。 など、感謝の声をたくさん頂き、この仕事をやって本当に良かったと日々思っております。
まずはスムーズで丁寧なやり取りを心がけています。 ご依頼主のお気持ちに沿う事が何よりと考えます。 お布施という分かりにくい料金設定も、明確な金額を提示させて頂きます。
その他特長などの紹介
2025/06
5
Q:檀家になる必要はありますか? A:いいえ。勧誘なども一切ありませんのでご安心下さい。 Q:追加のお布施がかかる場合がありますか? A:急なお布施、発生しません。本ページに記載があるものだけになります。ご安心下さい。 Q:どんな人におすすめですか? A:以下のような人に適しています。 ●お寺と付合がない方、日蓮宗希望の方 ●宗派にこだわりのない方 ●お葬式、49日忌法要等をご検討の方 ●墓や仏壇の供養をご検討の方 ●過去にお葬式やご法要に悔いのある方 初めてお葬式やご法要をご予定の方でも 丁寧にお話しを聞かせて頂き、 「悔いのない」「納得感のある」お葬式やご法要をお約束します。 安心して、おまかせください。 Q:お寺でお葬式や法事をすることはできますか? A:可能です。山梨県と静岡県 2つのお寺から選ぶことができます。 Q:当日の流れについて教えてください A: ①お伺い 私がご自宅にお伺いします。 ②ご挨拶 自己紹介、法務内容について改めてご挨拶させて頂きます。 ③法要執行 49日忌法要、ご位牌開眼供養法要などを執り行います。 ④法話 法要の意味、故人様に寄り添ったご法話お経文から選定し、お話しさせて頂きます。 ⑤ご挨拶 すべての法務が終わりましたら、改めてまして挨拶させて頂きます。このときに、お布施をお渡し頂ければ幸いでございます。 ⑥終了
50代~60代の女性で、お寺とのしがらみがなく、ご両親の供養してあげたいという利用者様が多いです。
一言でいうと、依頼者様の「本音」に寄り添ったお葬式やご法要を 全ての人にお届けしたいと考えています。 こんな体験をしました。 それは、お葬式に「喪主側の参列者」として参列したときのことです。 「住職の話は聞いたけど、なんか納得のいかない戒名だった。事前に戒名ってわからないの?」 喪主を勤めていた親戚にそういわれ はっと気づかされた瞬間でした。 通常、戒名は「お葬式の当日」になるまでわかりません。 わかったとしても「お葬式の30 分前」なので、変更したいと思ってもその猶予はありません。 この体験を通して、きっと喪主様が 住職には言えない「本音」がたくさんあるんだと気づかされました。 それ以来、お戒名をお付けする際は必ず喪主様に事前に戒名とその意味をご説明してから お葬式をさせて頂いております。 その方が喪主様も「悔いを残すことなく安心」して、故人様をお見送りできると考えたからです。 もちろん、崩してはならない掟もあり全てのご要望を通すことは難しいですが、 少しでも依頼者に「本音」に寄り添ったご法要をお届けしたい! という想いのもと、式を務めさせて頂いております。 ※これはあくまで私のやり方なので、他の住職様に強要されることのないようお願いいたします。
その他特長などの紹介
Q:檀家になる必要はありますか? A:いいえ。勧誘なども一切ありませんのでご安心下さい。 Q:追加のお布施がかかる場合がありますか? A:急なお布施、発生しません。本ページに記載があるものだけになります。ご安心下さい。 Q:どんな人におすすめですか? A:以下のような人に適しています。 ●お寺と付合がない方、日蓮宗希望の方 ●宗派にこだわりのない方 ●お葬式、49日忌法要等をご検討の方 ●墓や仏壇の供養をご検討の方 ●過去にお葬式やご法要に悔いのある方 初めてお葬式やご法要をご予定の方でも 丁寧にお話しを聞かせて頂き、 「悔いのない」「納得感のある」お葬式やご法要をお約束します。 安心して、おまかせください。 Q:お寺でお葬式や法事をすることはできますか? A:可能です。山梨県と静岡県 2つのお寺から選ぶことができます。 Q:当日の流れについて教えてください A: ①お伺い 私がご自宅にお伺いします。 ②ご挨拶 自己紹介、法務内容について改めてご挨拶させて頂きます。 ③法要執行 49日忌法要、ご位牌開眼供養法要などを執り行います。 ④法話 法要の意味、故人様に寄り添ったご法話お経文から選定し、お話しさせて頂きます。 ⑤ご挨拶 すべての法務が終わりましたら、改めてまして挨拶させて頂きます。このときに、お布施をお渡し頂ければ幸いでございます。 ⑥終了
50代~60代の女性で、お寺とのしがらみがなく、ご両親の供養してあげたいという利用者様が多いです。
一言でいうと、依頼者様の「本音」に寄り添ったお葬式やご法要を 全ての人にお届けしたいと考えています。 こんな体験をしました。 それは、お葬式に「喪主側の参列者」として参列したときのことです。 「住職の話は聞いたけど、なんか納得のいかない戒名だった。事前に戒名ってわからないの?」 喪主を勤めていた親戚にそういわれ はっと気づかされた瞬間でした。 通常、戒名は「お葬式の当日」になるまでわかりません。 わかったとしても「お葬式の30 分前」なので、変更したいと思ってもその猶予はありません。 この体験を通して、きっと喪主様が 住職には言えない「本音」がたくさんあるんだと気づかされました。 それ以来、お戒名をお付けする際は必ず喪主様に事前に戒名とその意味をご説明してから お葬式をさせて頂いております。 その方が喪主様も「悔いを残すことなく安心」して、故人様をお見送りできると考えたからです。 もちろん、崩してはならない掟もあり全てのご要望を通すことは難しいですが、 少しでも依頼者に「本音」に寄り添ったご法要をお届けしたい! という想いのもと、式を務めさせて頂いております。 ※これはあくまで私のやり方なので、他の住職様に強要されることのないようお願いいたします。
その他特長などの紹介
2024/10
5
Q お布施金額はどこを見ればわかりますか? A 当寺院のホームページを参照ください。
Q 法要を合わせた場合のお布施はどの様にになりますか? A 基本的には、プラス5,000円となります。
菩提寺にいらっしゃらない方、宗派にこだわらない方の葬儀、法要、墓前読教に対応します。
・葬式の読教 ・法事での読教 ・納骨、墓仕舞いの読教 ・墓前での年忌法要 ・当寺院への納骨と法要
・歴史ある寺院の住職が出張読経します。 ・お布施の明確化を心がけていますが、ご事情のある方はご相談下さい。 ・急なご依頼もスケジュール可能な限りお受けいたします。気軽にお声掛け願います。 ・色色なご事情に合わせ、対応させて頂きます。何でも、お気軽にお問合せください。 ・葬儀場、墓に新設、墓仕舞い、位牌の作成等信頼できる業者を紹介させて頂きます。
その他特長などの紹介
Q お布施金額はどこを見ればわかりますか? A 当寺院のホームページを参照ください。
Q 法要を合わせた場合のお布施はどの様にになりますか? A 基本的には、プラス5,000円となります。
菩提寺にいらっしゃらない方、宗派にこだわらない方の葬儀、法要、墓前読教に対応します。
・葬式の読教 ・法事での読教 ・納骨、墓仕舞いの読教 ・墓前での年忌法要 ・当寺院への納骨と法要
・歴史ある寺院の住職が出張読経します。 ・お布施の明確化を心がけていますが、ご事情のある方はご相談下さい。 ・急なご依頼もスケジュール可能な限りお受けいたします。気軽にお声掛け願います。 ・色色なご事情に合わせ、対応させて頂きます。何でも、お気軽にお問合せください。 ・葬儀場、墓に新設、墓仕舞い、位牌の作成等信頼できる業者を紹介させて頂きます。
その他特長などの紹介
60代以上 男性 香川県 観音寺市 会館での読教 一式 13万円 まだ若く、不慮による事案で、丁寧に厳かに厳修するよう心がけました。 七月初旬、友引を入れて3日間
会館での枕経、通夜、告別式、式中初七日(告別式に続いての初七日法要)の読教を行いました。 七条、袴の正式装束で行いました。
2024/06
5
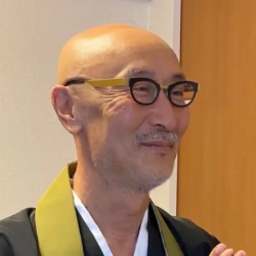
5
5
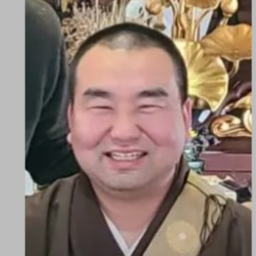
5
5

5
5
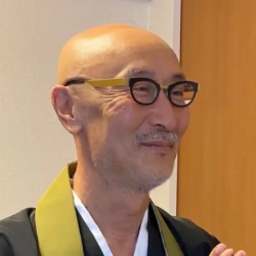
5
5
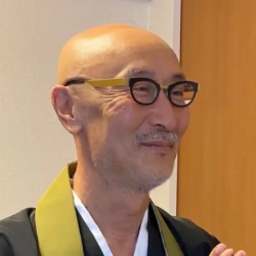
5
5
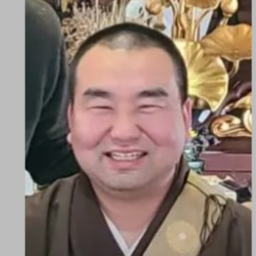
5
5
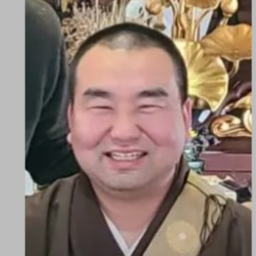
5
5
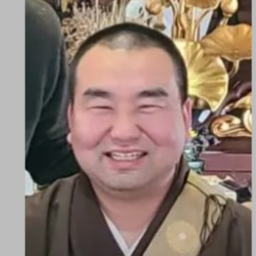
5
5
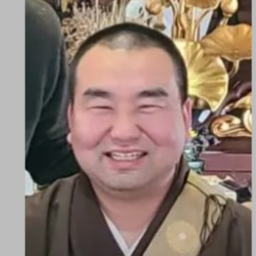
5
5
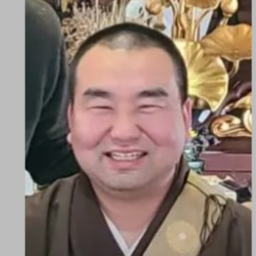
5
5