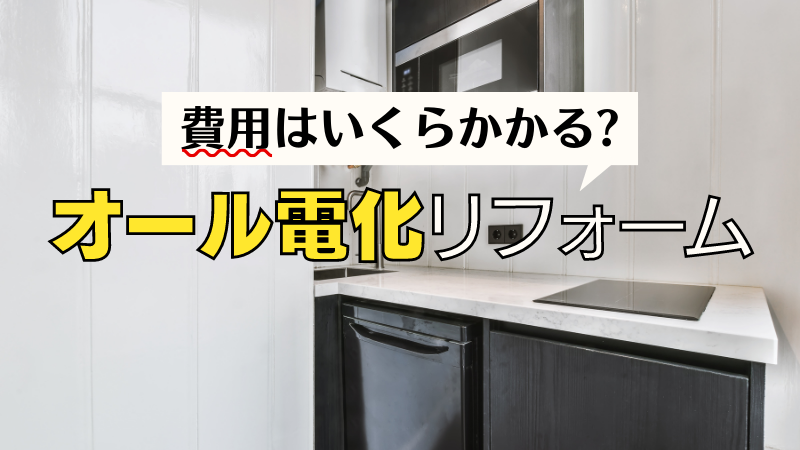オール電化リフォームの費用はいくらかかる?補助金制度も紹介!
オール電化リフォームとは住宅の熱源をガスではなく、電気でまかなうようにするリフォームのことです。オール電化リフォームには、光熱費を安く抑えられたり、災害時の復旧が早かったりなど、さまざまなメリットがあります。
一方、デメリットも存在するため、リフォーム前にはメリットとデメリットを勘案し、よく検討することが大切です。
今回は、オール電化リフォームのメリット・デメリット、リフォーム内容ごとの費用相場、さらに費用負担を抑えられる補助金・控除制度について解説します。オール電化リフォームを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
そもそもオール電化リフォームをするメリットとは?

オール電化リフォームとは、空調や給湯、調理などの熱源を、ガスではなくすべて電気でまかなうようにするリフォームのことです。
オール電化リフォームには、以下のようなメリットがあります。
- 光熱費を安く抑えやすくなる
- 基本料金を光熱費だけに絞れる
- 室内の空気が汚れにくくなる
- 災害時だと電気の復旧が早い
ここでは、オール電化リフォームをするメリットについて解説します。
光熱費を安く抑えやすくなる
すべての設備を電気でまかなうオール電化というと、電気代がかかるというイメージを持っている方もいらっしゃるでしょう。しかし、オール電化には、光熱費を安く抑えやすいというメリットがあります。
全国の電力会社によると、オール電化住宅の電気代の年間平均額は約19万円です。一方、ガスを使用している住宅の平均額は約23万円であり、価格を比較すると、オール電化の住宅の方が費用は安いことがわかります。
このように、光熱費を安く抑えたい方には、オール電化リフォームがおすすめです。
基本料金を光熱費だけに絞れる
電気とガスを併用する場合は、電気代とガス代のどちらにも基本料金がかかります。一方、オール電化ならガスを契約する必要がないため、基本料金を光熱費だけに絞れます。
ガスの基本料金が不要な分、一般的な住宅よりも、オール電化の住宅の方が光熱費を節約しやすいのです。
電力小売自由化がスタートしたことで、基本料金が不要のプランも登場しました。こうしたプランを利用することで、さらに電気料金を安く抑えられることが期待できます。
室内の空気が汚れにくくなる
ガスを利用した住宅の場合のリスクは、ガス漏れや不完全燃焼などにより、一酸化炭素中毒を引き起こすことです。また、ガスコンロを使用すると二酸化炭素が発生するため、空気が汚れてしまいます。
オール電化ならガスを使用しないため、一酸化炭素中毒の危険性がありません。また、IHクッキングヒーターは二酸化炭素が発生しないため、室内の空気が汚れにくいというメリットもあります。
災害時だと電気の復旧が早い
災害が発生してライフラインが途絶えてしまった際、ガスよりも電気の方が復旧は早い傾向にあります。
たとえば、2011年3月の東日本大震災では、停電の解消→断水の解消→ガスの復旧の順番にライフラインが復旧しました。とくに、ガスの復旧には時間がかかる場合が多いようです。
このように、災害時の復旧の早さを考えると、オール電化リフォームはメリットが大きいといえます。
オール電化リフォームをするデメリット

一方、オール電化リフォームには、以下のようなデメリットがあります。
- 電気代が高くなる恐れがある
- 設備の設置やリフォームの費用がかかる
- 調理器具の制限が生じる
- 停電になると使えなくなる
ここでは、オール電化リフォームを行うデメリットについて解説します。
電気代が高くなる恐れがある
オール電化によって、かえって光熱費が高くなってしまう可能性があります。
オール電化住宅向けの電気料金プランは、電気代が割安になる夜間の電力を利用するものがほとんどです。夜間の深夜料金が安い分、昼間の電気料金は高く設定されているケースが多くみられます。
たとえば、エコキュートは夜間に熱を蓄えて利用するため、お湯や暖房にかかる電気料金は安くなりやすいです。しかし、日中に使う調理機器や電化製品については、電気料金が高くなります。
また、温水が足りなくなって日中に沸き増しをすると、日中の電気料金が適用される点に注意が必要です。
このように、日中に多くの電気を利用する家庭の場合は、オール電化リフォームによってかえって電気代が高くなってしまうリスクがあります。オール電化リフォームを行う前に、業者に電気代のシミュレーションを依頼しましょう。
設備の設置やリフォームの費用がかかる
エコキュートや蓄熱暖房機、IHクッキングヒーターなどは、設置にあたって高い費用がかかります。たとえば、エコキュートの場合は、設置にあたって基礎工事や電気工事などが必要です。
本体費用のほかにさまざまな設置費用がかかるため、ガス給湯器の設置よりも、導入コストが高い点はデメリットといえます。
一方で、ガスを利用する場合よりも光熱費を節約できるというメリットもあるため、設置費用と後々の光熱費を勘案して、よく検討したうえでリフォームするか否かを決めましょう。
調理器具の制限が生じる
IHクッキングヒーターは電磁波で加熱するため、電気を通さない土鍋のような調理器具は、対応していません。ガスコンロに比べて、調理器具の制限が生じる点はデメリットです。
また、強い火力を必要とする鍋振り料理については、ガス調理のようには調理できない場合が多いため、注意が必要です。なかには、鍋振り料理に対応したIHクッキングヒーターもありますが、価格が高いというデメリットがあります。
停電になると使えなくなる
ガスと電気を併用している住宅の場合、停電になってもガス機器を使用できます。一方、オール電化住宅の場合は、給湯や調理、暖房など、さまざまな機器が使えなくなるため注意が必要です。
しかし、電気の方がガスよりも復旧にかかる時間が短い点を考えると、必ずしも不便とはいえません。また、停電時も使える機能を備えたタイプの製品も販売されているため、万が一のリスクに備えて製品を選ぶのもおすすめです。
【あわせて読みたい!】
最新版!エコキュートの買い替え費用は?選び方のコツや補助金もチェック>>>
床暖房にリフォームしたい!後付けの方法や費用をチェック>>>
オール電化リフォームの費用は内容によって異なる

オール電化リフォームの費用は、設備や内容によって費用が異なります。ここでは、リフォーム内容ごとの費用相場を解説します。
IHクッキングヒーターへのリフォーム費用
ガスコンロからIHクッキングヒーターへリフォームを行う場合には、ガスの撤去工事と、IH用の200V電源の設置工事が必要です。
IHクッキングヒーターへのリフォーム費用は、以下のとおりです。
| 本体価格 | 約4~15万円 |
| 配線機器・ブレーカー費 | 約1万円 |
| 配線工事費 | 約3万円 |
| 設置工事費 | 約2万円 |
本体価格と設置費用を合わせて、約10〜30万円ほどが相場となっています。
エコキュート・電気温水器へのリフォーム費用
オール電化住宅にリフォームする場合は、ガス給湯器の代わりに、エコキュートか電気温水器のいずれかを導入する必要があります。
ここでは、より電気代を抑えやすいエコキュートへのリフォーム費用を解説します。
| 本体価格 | 約15~30万円 |
| 脚部カバー | 約1万円 |
| ドライフレックスパイプ・継手ユニオン | 約5万円 |
| 風呂循環口 | 約9,000円 |
| 電線・電線管 | 約8,000円 |
| 接続材、支持材 | 約5,000円 |
| 漏電ブレーカー | 約4,000円 |
| プルボックス・野外用プラボックス | 約3,000円 |
| 工事費 | 約15万円 |
| 給湯器搬出・処分費 | 約3万円 |
本体価格や設置費用などを合わせて、トータル金額は約40~80万円です。
なお、本体の費用はタンクの容量によって異なります。容量が大きいものは費用が高くなりますが、その分多くのお湯を使えます。家族の人数やライフスタイルに応じて、適切なものを選びましょう。
また、給湯と床暖房をエコキュートのヒートポンプ1台で兼用できる多機能タイプもあり、機能性が高い分費用は高くなります。
床暖房へのリフォーム費用
オール電化住宅では、ガスや石油の代わりに、電気を熱源とする暖房器具を設置する必要があります。電気を使用する床暖房は、以下の2つです。
- 電気式床暖房:床暖房機器内の電気ヒーターで温める
- 温水式床暖房:電気で温水を作り、温水を床の下に流して温める
電気式床暖房は、導入費用が安いですが日中の電気代を使用するため、電気代が高くなる傾向にあります。ただし、長時間使用すると低温やけどのリスクがあり、温水式床暖房に比べると安心して使えるとはいえません。
一方、温水式床暖房は、夜間にエコキュートで沸かしたお湯を使用するため、電気代を安く抑えられます。安全性や電気代の安さから、温水式床暖房の方が人気は高いです。ただし、電気式床暖房に比べると、導入にあたってコストがかかる点に注意しましょう。
電気式床暖房の導入費用相場は約6万円〜10万円、温水式床暖房の場合は約30〜40万円です。温水式床暖房の設置にかかる費用内訳は、以下のとおりです。
| ヒーター | 約12~14万円 |
| 専用コントローラー | 約2万円 |
| フローリング材 | 約6~8万円 |
| 床断熱材 | 約1万円 |
| 人件費 | 約5~6万円 |
| 電気設備工事 | 約3~4万円 |
| 金物接着剤費 | 約6,000~7,000円 |
オール電化住宅では、多機能型のエコキュートが人気であり、給湯と暖房兼用で熱源を用意するケースが多くみられます。
太陽光発電へのリフォーム費用
オール電化住宅では、太陽光発電を併用するケースが多いです。太陽光発電を導入すれば、電気代が高い昼間は太陽光パネルで発電した電気を利用できます。そのため、電気代を削減しやすいのが特徴です。
また、家庭で消費しきれなかった電力については、電力会社に売電できます。
太陽光発電を導入する際は、以下のような費用が必要です。
| 本体価格 | 約130~230万円 |
| パワーコンディショナー | 約22万円 |
| モニター | 約5万円 |
| 設置架台 | 約12万円 |
| 架台工事費 | 約7万円 |
| 太陽電池モジュール設置工事費 | 約15万円 |
| 配線設備費 | 約3万円 |
| 電気配線工事費 | 約12万円 |
このように、本体価格や設置費用などを合わせて、トータルで約200〜300万円ほどかかります。地方自治体によっては、条件を満たせば補助金や助成金を利用できるため、費用を削減できることもあります。
オール電化リフォームで活用できる補助金・控除制度

最後に、オール電化リフォームにあたって活用できる補助金・控除制度をご紹介します。
- すまい給付金
- 省エネ改修に関する特例措置
- 長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
補助金や控除制度を利用することで、設備の交換・導入にかかる費用負担を軽減できます。ぜひ利用してみてください。
すまい給付金
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。リフォーム住宅についても、対象となります。
| 対象 | 住宅(リフォーム・新築) |
| 要件 | ①住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者 ②住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者 ③収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円[10%時]収入額の目安が775万円 ④(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者 |
| 補助金額 | 給付額は、住宅取得者の収入および持分割合により決定される |
収入や持分割合によって、補助金額が変わる仕組みです。詳細は、以下をご覧ください。
参考:すまい給付金(国土交通省)
省エネ改修に関する特例措置
省エネ改修に関する特例措置とは、住宅の省エネ性能を向上させるリフォーム工事を行った際、改修後に居住を開始した年の所得税額が、一定額控除される仕組みです。太陽光発電の導入や省エネ機器の設置などが、対象となります。
| 対象 | 太陽光発電・省エネ機器・住宅(リフォーム・新築) |
| 要件 | ①その者が主として居住の用に供する家屋であること ②工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること ③床面積が50平方メートル以上あること ④店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること ⑤合計所得金額が3,000万円以下であること |
| 補助金額 | 以下、(ア)および(イ)の合計額が所得税から控除される (ア)一定の省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円まで):10%を控除 (イ)以下、①、②の合計額:5%を控除ただし、(ア)と合計で1,000万円まで ①(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額 ②(ア)以外の一定の増改築等の費用に要した額((ア)と同額を限度) |
補助金額の仕組みが複雑であるため、正しく理解する必要があります。詳細は、以下をご覧ください。
参考:省エネ改修に関する特例措置(国土交通省)
長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
長期優良住宅化リフォームに関する特例措置は、一定の耐震改修や省エネ改修とあわせて耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を行い、長期優良住宅の認定を取得する場合に利用できるものです。改修後、居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。
| 対象 | 太陽光発電・省エネ機器・住宅(リフォーム・新築) |
| 要件 | ①工事を行った者が主として居住の用に供する家屋であること ②工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること ③床面積が50平方メートル以上であること ④店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること ⑤合計所得金額が3,000万円以下であること |
| 補助金額 | 一定の耐震改修、または一定の省エネ改修工事および一定の耐久性向上改修工事に係る、標準的な工事費用相当額の10%がその年分の所得税額から控除される ※投資型、ローン型減税のいずれかを選択 |
対象となる工事にはさまざまな要件が定められているため、確認が必要です。詳細は、以下をご覧ください。
参考:長期優良住宅化リフォームに関する特例措置(国土交通省)
リノベーション業者のプロを探す

オール電化リフォームのメリットやデメリット、リフォーム内容ごとの費用相場、さらに費用負担を抑えられる補助金・控除制度について幅広く解説しました。オール電化リフォームを考えている方はしっかり検討してから進めるのをおすすめします。
- オール電化リフォームについて相談したい
- オール電化リフォームをする場合の見積もりをとりたい
そんな方は、ゼヒトモからリノベーション業者のプロを探してみませんか?いくつかの質問に答えるだけで、簡単にあなたにピッタリなプロが見つかります。
オール電化リフォームを検討している方は、ゼヒトモお気軽にご利用ください!
リノベーション関連の最新記事
近年は、押入れをおしゃれなクローゼットとして活用するケースが増えていて、リノベーションする方も多くなっています。ただ実際業者に依頼するとなると、気になりがちなのが費用の相場。 そこで今回は、押入れをクローゼットにしたい時 […]
庭の一部を潰して部屋や離れ、サンルームなどを増築すると、リラックススペースや生活スペースを拡げられます。ただし、庭の一部を潰すリフォーム工事を進める場合、さまざまな点を確認しなければなりません。どのような点に注意すべきで […]
あなたのお困りごとをプロに相談してみよう
2分でスマホやPCで簡単に依頼内容を入力します。
最大5人のプロから提案を受けられます。あなたの条件に合うプロを採用してください。
プロと相談した場所・日時・値段で依頼したサービスを受ける。